|
令和7年10月14日(火)
|
|
| 昨日、ウォーキングの後、剪定枝の束ねを完了しました 昨日もどんよりと曇った朝を迎えました。 その後太陽は出てきましたが、曇り気味の一日でした。 そのためふとんを干すことはあきらめました。 パソコンの一日でした。 電力の問題問13を終えることができました。 祝日のため株の勉強は休みでした。 夕刻は買い物は午後3時に出発して兼ねてウォーキング60分でした。 帰宅後、蚊に悩まされながら、剪定枝を束ねました。 なんとか本日の提出に間に合いました。 庭を見渡すと枝の剪定個所が沢山あります。 これから焦らずじっくりと取り組みたいと思います。 |
|
| 「人質広場」に響く歓喜の声 戦闘終結の一歩、ガザ和平へ残る課題は 朝日新聞の記事です。 2年にわたって続けられてきたパレスチナ自治区ガザでの戦闘は13日、重大な局面を迎えた。 イスラエル側の悲願だった生存する人質の全員解放が実現し、多数のパレスチナ人収監者らも釈放された。 イスラエル政府とイスラム組織ハマスに加え、和平案を主導したトランプ米大統領も成果をアピールするが、イスラエル軍の完全撤退やハマスの武装解除などをめぐる対立点は残り、戦闘終結への道筋は見通せない。(以下、省略) 人質の開放は終わったようです。 これで戦闘が終わり平和な日が来ることを願っております。 |
|
 イスラム組織ハマスが人質を解放したと伝えるテレビ中継を見て喜ぶ人たち =2025年10月13日、イスラエルのテルアビブ、真野啓太撮影 |
|
| 「別世界」つくった万博、分かれた見方 国費1700億円投じた責任 世界各地で自国ファーストの訴えが共感を集め、排外主義的な主張がSNSから街頭へ広がる。 ウクライナをはじめ、戦争や分断もやむことがない――。 大阪・関西万博が開かれたこの半年間、国内外はそんなニュースに満ちた。(以下、省略) 大阪・関西万博が閉幕しました。 来場者は予想以上であったとのことです。 |
|
 大屋根リングの下を行進するミャクミャクと日本国際博覧会協会の十倉雅和会長(左から3人目)ら =2025年10月13日午後4時45分、大阪市此花区、有元愛美子撮影 |
|
| 野党候補への投票「可能性の一つ」 公明代表、首相指名の決選投票で 朝日新聞の記事です。 公明党の斉藤鉄夫代表は13日のBS日テレの番組で、臨時国会の首相指名選挙で決選投票になった場合の対応について、野党候補への投票を「可能性のうちの一つだ」と述べた。 「あらゆる可能性の中から、最終的には党で話し合って決める」とも語った。(以下、省略) 公明党の動きが注目されております。 宙ぶらりんの公明党です。 |
|
 2025年10月10日、自民党の高市早苗総裁との会談後、記者会見で連立政権からの 離脱を表明する公明党の斉藤鉄夫代表=国会内、岩下毅撮影 |
|
今日は何の日 (出典 雑学ネタ帳)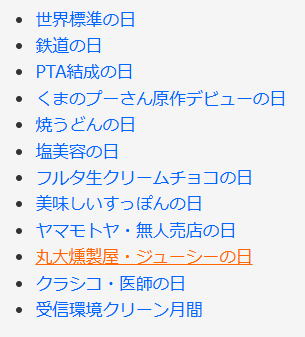 世界標準の日(10月14日 記念日) 国際標準化機構(International Organization for Standardization:ISO)と国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission:IEC)が1960年(昭和35年)に制定。 記念日の英語表記は「World Standards Day」または「International Standards Day」。 1946年(昭和21年)のこの日、25ヵ国がイギリス・ロンドンに集まって、標準化を促進するための世界的な組織を創設することを決定した。この日は世界標準を策定した人たちに感謝し、労をねぎらう日である。また、標準の管理者・業界・消費者に対して、世界経済の標準化の重要性について意識を高めるための日である。 この日を含む10月1日〜31日までの一ヵ月間を「工業標準化月間」として各国で標準化の強化活動が行われる。 日本では、1954年(昭和29年)に「工業標準化振興週間」を開始し、1994年(平成6年)から「工業標準化推進月間」に改めた。また、2019年(平成31年)から「産業標準化推進月間」に改め、普及活動のため、各種広報・表彰・講演会の開催などを実施している。 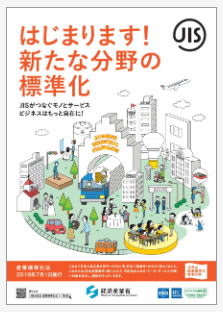 「産業標準化推進月間」ポスター 世界標準について 世界標準(international standard)は、各国の様々な規格や基準を世界で統一化することで円滑な国際交易をはかるためのもので、国際工業規格・国際会計基準などがある。交通信号機が緑・黄・赤の3色となっている事例や、船舶や航空機が右側通行に統一されていることなどが世界標準の例である。 日本では国際標準から派生して生まれた比喩的な表現の言葉にグローバル・スタンダード(global standard)がある。グローバル・スタンダードという言葉が、日本で多用されるようになったのは1997年(平成9年)以降であり、日本国外ではあまり使用されない和製英語と言われている。 |