|
令和7年01月11(土)
|
|
| 昨日、午前中は酒の量販店へビールの買い出し → 午後はケーオーへの買い物 → 帰宅後、金柑の採取 昨日も朝から太陽が出て、ほぼ一日中晴れの良い天気でした。 午前中は酒の量販店へビールの買い出しへ行きました。 電池のない電動自転車で行きましたが、帰りに北風の向かい風に会い府中の刑務所から歩きとなりました。 ビールは1ケースでしたがとてもくたびれました。 これで2月いっぱいは応えられます。 午後はケーオーへの買い物を兼ねてウォーキング60分間しました。 帰宅後、金柑の採取をしました。 高く伸びている枝の撤去に徹しましたので、実の収穫は時間の割にありませんでした。 お陰で通路のコンクリート打ちの準備は全くできませんでした。 現在インフルエンザが流行っているようです。 健康管理には十分注意をしたいと思っております。 |
|
| 成田空港、34万回に発着枠拡大へ 世界で薄れる存在感、回復へ一歩 朝日新聞の記事です。 成田空港(千葉県)の年間発着枠の上限について、国土交通省が現在の30万回から34万回に拡大する方針を固めたことが分かった。 今月下旬に地元自治体などで構成する四者協議会で提案し、10月からの実現を目指す。 アジアの空港間競争が激化するなか、増加する航空需要を取り込むための取り組みが本格化する。(以下、省略) 本日の新聞の1面のトップ記事です。 外国人の利用が多いために拡大されるという。 事故が増えなければいいがと心配です。 |
|
 年間発着枠が34万回に拡大される成田空港 =2024年5月、千葉県成田市、朝日新聞社ヘリから |
|
| 裁判官を辞めさせた弾劾裁判、3時間で打ち切られた議論 その内幕は 朝日新聞の記事です。 高い独立性を守るため、身分が手厚く保護される裁判官。 その職を奪う例外的な手段である弾劾(だんがい)裁判の結論を決める「評議」が、3時間で終わっていた。 評議の実態が明らかになるのは異例だ。(以下、省略) 弾劾裁判は、「裁判官を辞めさせるかどうか」を決めるための特別な裁判だ。弾劾裁判で「罷免(ひめん)」、つまり辞めさせるべきだと判断されれば、その裁判官は職を失う。 |
|
 裁判官弾劾裁判所に入る岡口基一・仙台高裁判事(右) =2024年4月3日午後1時43分、東京・永田町、上田幸一撮影 |
|
| 法政大の教室に響いた「キャー」 散り散りに逃げる学生「怖かった」 朝日新聞の記事です。 午後4時前、社会学部棟2階の大教室。 社会学部2年という女性(20)は100人ほどが授業を受ける大教室の右後ろに座っていた。 「キャー!」。 いきなり、自身の座る席から左側の方向からそんな女性の叫び声が聞こえた。 目をやると、周りの学生が散り散りに走りながら、逃げ始めたのが見えた。 逃げる人のなかには、顔に血がついた女性もいたという(以下、省略) 周囲のみんなから無視されていたために事故を起こしたという。 短気な女性がいたものです。 |
|
 女がハンマーを振り回したとされる法政大多摩キャンパス。 多くの捜査車両が集まっていた =2025年1月10日午後5時12分、東京都町田市相原町、岡田昇撮影 |
|
今日は何の日 (出典 雑学ネタ帳)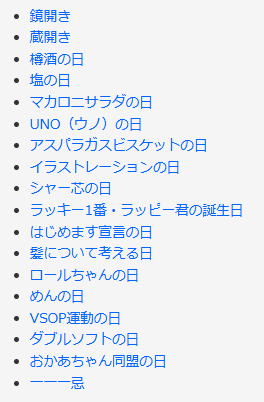 鏡開き(1月11日 年中行事) 正月に神(年神)や仏に供えた鏡餅を下げて食べる日とされる。  鏡開き 神仏に感謝し、また無病息災などを祈って、汁粉や雑煮などで食す。武家では鏡餅を刃物で切ることは切腹を連想させるため、手や木槌で割る風習があった。また、「切る」「割る」という言葉は避けて「開く」という言葉が使われた。 商家では新年の初めに蔵を開いて商売繁盛を祈る行事をこの日に行う。「鏡」は円満を、「開く」は末広がりを意味する。鏡餅の割れ方で占いをする地域もあり、「鏡餅の割れが多ければ豊作」と言われている。 もとは松の内が終わる正月15日「小正月」の後の20日に行われたが、江戸時代に11日に改められた。現在まで続く風習であるが、その日は1月11日に限らず、京都の一部では1月4日、松の内が1月15日の地方では1月20日に行われるなど、地方によって異なる場合もある。 |