| 9 | 日本三古湯 日本で古くからの歴史がある温泉のことで、一般的には、道後温泉(愛媛県)、有馬温泉(兵庫県)、白浜温泉(和歌山県)またはいわき湯本温泉(福島県)の三つを指します。 いずれも、神話の時代からの長い歴史を有しております。 各種HPより、まとめました。 |
|
| 道後温泉(どうごおんせん) (愛媛県松山市) 温泉の歴史は古く、「伊予温湯(いよのゆ)」「熟田津石湯(にぎたつのいわゆ)」などという。『日本書紀』『万葉集』『伊予国風土記(ふどき)』逸文、『源氏物語』などにその記述がみられ、わが国最古の温泉の一つである。火山性温泉とは異なり、領家花崗(りょうけかこう)岩帯に貫入した黒雲母(くろうんも)花崗岩の裂け目から湧出(ゆうしゅつ)する温泉である。道後湯之町(ゆのまち)を通り、北西―南東方向に断層があって、源泉の多くはこの破砕帯にあり、十数か所現存する。断層の上部は厚い沖積層に覆われているので、源泉垂直深度は大きく300〜500メートルに達する。泉質は単純アルカリ質、湧出量は毎分100〜200リットルだが変動がある。1946年(昭和21)の南海地震では一時湧出が停止した。道後温泉本館(振鷺(しんろ)閣)は明治中期の建物で、神之湯、霊之湯(たまのゆ)、休憩所からなる共同浴場である。ほかに数か所の共同浴場があり、旅館・ホテルは約100軒を数える。各種娯楽施設、土産(みやげ)物店などがあり、一大温泉街をなしている。予讃(よさん)線松山駅から伊予鉄市内線が通じる。 |
 |
|
| 有馬温泉(ありまおんせん)(兵庫県神戸市北区) 泉質は鉄分を含む強塩類炭酸泉。古くからの温泉地として知られ、『日本書紀』には舒明(じょめい)天皇来訪の記載がある。僧行基(ぎょうき)はここに温泉寺を開いたという。また僧仁西(にんさい)が温泉を復興し、12の僧坊を建立。今日でも温泉に「中の坊」「御所の坊」などの名が付されている。豊臣(とよとみ)秀吉はたびたび湯治に訪れており、荒れていた温泉復興に力を尽くした。大阪、神戸に近く、閑静な保養地として知られ旅館街の近代化が進んでいる。温泉神社では正月に行基と仁西の木像に湯を注ぐ入初式があり秀吉をしのぶ茶会も催される。 |
 湯泉神社 |
|
| 白浜温泉(しらはまおんせん)(和歌山県白浜町) 1919年(大正8)湯崎温泉の北部に土地会社により採掘された。現在では湯崎温泉をも包含して白浜温泉とよんでいる。泉質は食塩重曹泉。 南紀白浜温泉(なんきしらはまおんせん)、もしくは白浜温泉(しらはまおんせん)は和歌山県西牟婁郡白浜町にある温泉である。温泉として非常に歴史が古く、日本三古湯のひとつに数えられる。古い文献では牟婁の湯と呼ばれていた。広義での白浜は温泉郷であり、さらに湯崎、大浦、古賀浦などさらに5つの温泉地に細分できる。海岸沿いに温泉施設、宿泊施設が広がっており、西日本有数のマリンリゾートとしても発展している。 |
 1300年余りの歴史をもつ「崎の湯」 |
|
| 湯本温泉(福島県いわき市) 発見は遠く景行天皇の御代にはじまる、往昔は日本名湯の一つとして知られ、"あかずして別れし人の住む里、さはこのお湯の山のあなたか"と歌が拾遺物にもあり1,600年の歴史をもつ。 常磐炭田の真中にあり、明治に至って一時湯量が減じたがその後炭坑内に往年にまさる大湯出があり、現在の繁栄をみるに至った。 温泉街は駅から5分、優雅な鈴蘭燈並ぶ近代的な街路に沿って炭坑の見える海に近い温泉郷として独特の情緒があり名物ジャンガラ囃子、炭坑節が流れて旅情を誘う。 |
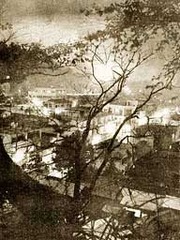 |
|